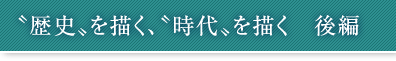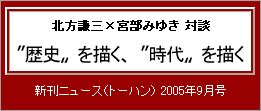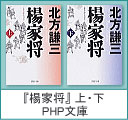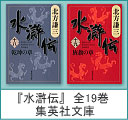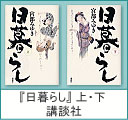| 宮部 |
: |
北方さんの新刊『絶海にあらず』は藤原純友が主人公ですが、資料はほとんど残っていなかったのではないですか。かなり難しい人物だったと思うのですが。 |
| 北方 |
: |
難しかったです。日本で反乱を起こした人、あるいは権力に逆らって死んでいった人というのはいろんな民間伝承が残っているんです。例えば、平将門などは数々の伝説を残しています。でも、藤原純友に関しては皆無でした。 |
| 宮部 |
: |
なぜ純友に興味を持たれたんですか。 |
| 北方 |
: |
日本の動乱をずっと探ってみると、一番わかりやすいのは「大化の改新」なんです。それから律令制というものができて日本は発展していって、それが武家社会に変わる。武家社会がどこまで続いたかというと、第二次世界大戦までなんですね。 |
| 宮部 |
: |
軍隊を武家社会と考えるわけですか。 |
| 北方 |
: |
いえ、軍隊ではなく指導者をね。指導者層を武家社会と考えると、武家支配というものがずっと続いていたと言えるわけです。政府の中にも、海軍の中にも、陸軍の中にも薩摩閥があり、長州閥があったんだから。 |
| 宮部 |
: |
閥が藩単位で動いていたわけですよね。 |
| 北方 |
: |
マッカーサーがくるまでこれはずっと続いていた。だから、日本には武家支配の体制と律令体制の二つの大きな体制があったわけです。武家支配の中での反乱というのはいくらでもあったんだけど、律令制の中の反乱というのは実はあんまりなくて、一番大きかったのが平将門と藤原純友が起こした「承平・天慶の乱」だった。 |
| 宮部 |
: |
まさしく『絶海にあらず』の舞台ですね。 |
| 北方 |
: |
将門は土地を支配しようとして乱を起こし、純友は海上の物流制限を取っ払おうとして乱を起こした。この二つの対照的な乱の中で俺が純友に興味を持ったのは、純友の物流への考え方といのが現代と非常に似ていたからなんです。権力による規制を是とせず、海上での自由な物流を目指したわけです。 |
| 宮部 |
: |
純友は栄耀栄華を極めた藤原一族の中でははぐれ者だった、というところにも魅力を感じられたのではないですか。 |
| 北方 |
: |
藤原北家は権力を持っていたんだけど純友は傍流だった。努力して出世したとしても、せいぜい最下級の貴族ぐらいにしかなれなかったんです。正統な藤原家だと、バカでもどんどん出世していく。純友はそういうのはおかしいと考えていた。 |
| 宮部 |
: |
生まれた時からハンデがあるわけですからね。 |
| 北方 |
: |
そういう背景があったから、小説の中での純友は出世競争に興味がないという人物設定にしたんです。 |
| 宮部 |
: |
既成の体制の中で出世しようとして汲々とするんじゃなくて、もっと自分の心に正直に生きるという… |
| 北方 |
: |
そうです。そういう人物設定にしてはみたんだけど、現実問題として純友は早い段階で出世するんです。でも、上の言うことは全然守らなかった。 |
| 宮部 |
: |
北方さんが好まれそうな人物ですね。『絶海にあらず』の執筆中は、楽しかったんじゃないですか? |
| 北方 |
: |
俺、これを書いてるときに中国ものの『楊家将』や『水滸伝』を書いていたんです。そうすると頭の中が中国でいっぱいになっている。 |
| 宮部 |
: |
切りかえるのが大変そう。 |
| 北方 |
: |
『絶海にあらず』を書く時は、中国からいきなり平安時代に戻るわけじゃない。これがね、すごく快感だった(笑)。 |
| 宮部 |
: |
快感ですか(笑)。『絶海にあらず』も『楊家将』も新聞連載でしたよね。 |
| 北方 |
: |
うん。 |
| 宮部 |
: |
そうすると、月の中でどういうふうに仕事のスケジュールを割り振っていらしたんですか。一週目は『絶海にあらず』で、二週目は『楊家将』とか、そういう感じですか。 |
| 北方 |
: |
そのへんは適当です。 |
| 宮部 |
: |
エエッ! |
| 北方 |
: |
締切が近くなったら書いて渡すという感じかな。一番大変なのは「小説すばる」に連載していた『水滸伝』の百五十から二百枚でしたね。二百枚を四日で書くとなるとさすがに大変でした。 |
| 宮部 |
: |
それはすごい。 |
| 北方 |
: |
昼か夜かわからない状態で書いている。だけど、そうやって書いた方が、たっぷり時間を使って書いたよりも、何でこんなことが書けたんだろうと思うようなことが書けるんだよね。 |
| 宮部 |
: |
エモーションは高まりますよね。ただ、それは作家としてのパワーと基礎体力があるからできることなんでしょう。普通は途中でバテますって。私なんか百枚を四日で書いてもバテますから。例えば、二百枚を十日で書くとしたら、一日二十枚ずつ書くよりは、一日四十枚を何日間かにわけて書いた方がいいですよね。でも、四日で二百枚は無理。書けない人の方が多いと思います。 |
| 北方 |
: |
俺はそれを六年近くやってきた。一回も休まなかったし。 |
| 宮部 |
: |
北方さんはぎっくり腰をなさった時も、画板を買ってきてもらって、仰向けで原稿をお書きになったことがあるんですよね。 |
| 北方 |
: |
ある、ある(笑)。いつもは万年筆で書くんだけど、仰向けで書くとインクが出ないから鉛筆で書いたんだ。 |
| 宮部 |
: |
「ぎっくり腰のときぐらい休めばいいのに、よっぽど書きたかったんだろうね」って私たちは言っていました。 |
| 北方 |
: |
そう、書きたかったんだ(笑)。俺はやっぱり書くことが好きなんだよな。 |